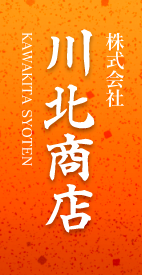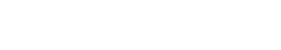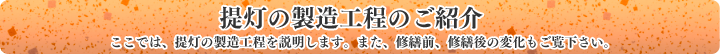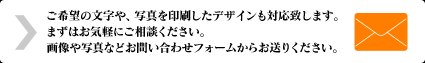ホーム >提灯とは

ろうそく用の灯火具。球形・円筒形・なつめ形などいろいろあるが、いづれも細い割竹(ひご)をらせん状にに巻いて骨とし、これに紙を張り、上下に口と底を取り付け、折り畳みできるようにしてある。おもに夜間の外出に携行したが、夜間屋外の目標や照明として掲げる事も多かった。
これを挑灯・提灯と書いてチョウチンと読むのは、室町時代の禅家の宋音に基づくと言われてる。始め挑灯は木枠に紙を張ったつり灯籠(とうろう)のようなものであり、次いで籠に紙を張り、取っ手をつけて持ち歩く籠挑灯となったが、やがて割竹を巻いて紙を張り、折り畳みができるものになり、便利な手に提げる灯火具というところから、提灯の字があてられる様になった。
この新しい提灯が使われるようになるのは文禄年間(1593~96)で、これが江戸時代になると在来の行灯(あんどん)にかわって流行し、各種の提灯が作り出された。
初期に作られていたのは、はこ提灯と呼ばれたもので、折り畳むと一個のはこになるように作られていて、始め儀式に用いられたが、のち遊里で客の送迎に用いられるようになった。
ブラ提灯は棒の先端にぶら下げて持ち歩いたのでこの名がある。広く一般庶民に用いられたが、武士が馬上に用いた馬乗提灯はその上級品である。
ほおずき提灯もその一種で、赤・紅白などの色彩を施した小型の提灯で、今も提灯行列や祝賀装飾などに用いられている。
弓張提灯は竹弓の弾力を利用して火袋を上下に張って安定させたもので、火消し人足や御用聞きをはじめ広く商家でも使用した。
高張提灯は大型の提灯を長竿の先につけたもので、これに定紋・屋号などを書き、社寺の門前や商家の店頭、行列の先頭に掲げて目標とした。
つり提灯も大型の提灯で社寺への献灯や祭礼の御神灯として用いた。

-
①字入れ・紋入れ
まず和紙に字や紋や柄を書き入れます。

-
②木型にひご巻き
木型を組み、らせん状にひごを巻く。
その後、型の間隔を均等にする
(左記は、ワイヤーですが、種類によっては、竹ひごを使います。) 。

-
③糸かけ
まず和紙に字や紋や柄を書き入れます。

-
④糊つけ
糊をひごの上に乗せるように均等に付けていきます。

-
⑤紙張り
位置がずれない様に、素早く紙を乗せ撫でるように刷毛で押さえる。重なり目はカミソリで切り張り合わせる。

-
⑥仕上げ
乾燥したら型から外し、口輪を付け、手・鋲を付け、仕上げる。 この後、油を引き、乾燥させたら出来上がりです。